相続登記を自分でやる方法!手続きの流れと費用をわかりやすく解説

2025年7月18日
目次
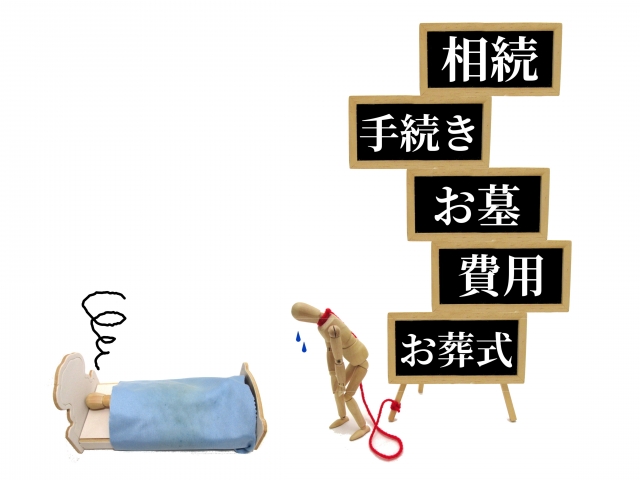
相続登記を自分でやるときは、費用と必要書類を把握しておきましょう。
手続きの流れがわかると、司法書士に依頼しなくても自分で相続登記できます。
本記事では、相続登記を自分でやるメリットやデメリット、手続きの流れなどをわかりやすく解説します。
相続登記とは?
相続登記とは、相続した不動産を自分の名義に書き換える手続きです。
法務局に相続登記を申請すると、土地や建物が自分の名義になるため、親族や第三者に対して所有権を主張できます。
不動産の名義が被相続人(亡くなられた人)のままだと、基本的に土地・建物の売却や活用はできません。
2024年4月1日以降は相続登記の義務化が始まったため、「不動産の相続人が確定してから3年以内」に登記申請する必要があります。
相続登記を自分でやるときは、まず手続き全体の流れや必要書類、費用などを理解しておきましょう。
相続登記を自分でやるかどうかの判断基準
相続登記をインターネットで検索すると、「相続登記を自分でやった」などのブログが見つかります。
しかし、相続の状況は個別に異なるため、同じように手続きが進むとは限りません。
相続登記を自分でやるかどうか迷ったときは、以下の判断基準を参考にしてください。
相続登記を自分でやってもよいケース
相続の状況が以下のようなケースであれば、相続登記を自分でやってもよいでしょう。
- 相続人が配偶者と子どもだけの場合
- 平日に時間を確保しやすい場合
- 行政手続きに抵抗がない場合
相続人が配偶者と子どもだけであれば、戸籍謄本などの取得に時間がかかりません。
市町村役場や法務局は平日のみ開庁しているので、退職している方や、有給休暇を取りやすい方は、相続登記の完了までがスムーズです。
行政手続きに抵抗がない方は、法定相続人の確定や、登記申請書の作成にも対応できるでしょう。
相続登記を司法書士に任せた方がよいケース
相続登記を自分でやるつもりだったところ、途中で挫折する場合があります。
不動産や相続人が以下の状況だったときは、相続登記を司法書士に任せた方がよいでしょう。
- 不動産がご先祖様の名義になっている場合
- 被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合
- 代襲相続人がいる場合
- 相続登記する不動産が多い
- 対立関係の相続人がいる場合
- 換価分割や代償分割をする場合
- 相続登記の期限が迫っている場合
不動産がご先祖様名義だった場合、生存している子孫に連絡し、全員の同意を得なければ相続登記はできません。
相続の当事者に兄弟姉妹や代襲相続人がいる場合は、取得する戸籍謄本が多くなるでしょう。
換価分割や代償分割は現金の受け渡しが発生するため、遺産分割協議書の書き方によっては贈与税がかかります。
相続登記の期限を過ぎると、10万円以下の過料になる恐れがあるので、時間に余裕がないときは司法書士に依頼してみましょう。
相続登記を自分でやるときの流れ
相続登記を自分でやるときは、以下の流れで手続きを進めます。
- 必要書類の取得
- 法定相続人の確定
- 遺産分割協議(遺言書がない場合)
- 登録免許税の計算
- 相続登記申請書の作成
- 管轄法務局へ相続登記を申請する
遺産分割協議は全員の同意によって成立するため、相続登記に半年から1年程度かかる場合もあります。
では、相続登記の必要書類や、費用などをみていきましょう。
必要書類の取得
相続登記を自分でやる場合、まず以下の書類を取得します。
【市町村役場で取得する書類】
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本:1通450円
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票:1通300~400円
- 相続人全員の現在戸籍:1通450円
- 相続人全員の印鑑証明書:1通200~300円程度
- 名寄帳:1通200~400円程度
- 固定資産評価証明書:1通200~400円程度
【法務局で取得する書類】
- 登記事項証明書:1通480~600円
【自分で準備する書類】
- 遺産分割協議書または遺言書
- 委任状(相続登記を代行してもらう場合)
被相続人の戸籍謄本を取得する際は、最寄りの市町村役場で「広域交付制度」を利用してみましょう。
法定相続人の確定
被相続人の戸籍謄本をすべて取得したら、以下の法定相続人を確定します。
- 配偶者:常に相続人となる
- 第1順位の法定相続人:被相続人の子ども
- 第2順位の法定相続人:被相続人の父母
- 第3順位の法定相続人:被相続人の兄弟姉妹
第1順位の法定相続人には前妻の子や養子、認知された非嫡出子(婚姻関係にない男女間の子)も含まれます。
子どもの認知には「遺言認知」という方法もあるので、遺言書があるかどうかも調べておきましょう。
遺産分割協議(遺言書がない場合)
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決める話し合いです。
協議がまとまったら遺産分割協議書を作成しますが、不動産は書き方を間違えやすいので注意してください。
土地は地番や地積(面積)、建物は家屋番号や床面積などを記載するため、登記事項証明書の確認が必要です。
一般的な住所表記にすると、法務局が相続登記の申請を受理してくれません。
遺産分割協議書の書き方に不安があるときは、司法書士に作成してもらいましょう。
登録免許税の計算
不動産を相続する場合、登録免許税がかかります。
登録免許税は以下のように計算し、不動産の所在地を管轄する法務局に納めます。
- 登録免許税:不動産の固定資産税評価額×税率0.4%
固定資産税評価額は納税通知書に同封される「課税明細書」、または「固定資産評価証明書」で確認してください。
相続登記申請書の作成
遺産分割協議がまとまったら、相続登記申請書を作成します。
相続登記申請書は法務局の窓口でもらえますが、法務局のホームページからダウンロードすると便利です。
登録免許税は収入印紙で納付するため、相続登記申請書とは別に「収入印紙貼付台紙」を作成し、中央部分に貼り付けてください。
収入印紙貼付台紙は白紙のA4用紙で構いません。
申請先の法務局についても、法務局のホームページで支局や出張所などを確認しておきましょう。
参考元:不動産登記の申請書様式(法務局)
参考元:各法務局のホームページ
管轄法務局へ相続登記を申請する
相続登記申請書を作成した後は、管轄法務局に相続登記を申請します。
登記申請の際には、以下の書類を提出してください。
- 相続登記申請書
- 収入印紙貼付台紙
- 遺産分割協議書または検認済の遺言書
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を提出する場合)
- 不動産を相続する人の現在戸籍
- 不動産を相続する人の住民票
- 固定資産評価証明書
相続登記の手続きは10日程度で完了しますが、特に通知はないため、法務局に出向いて確認します。
手続きの完了後は登記識別情報(不動産の権利証)が交付されるので、失くさないように注意してください。
相続登記を自分でやるメリットとデメリット
相続登記を自分でやるときは、必ずメリットとデメリットを比較してください。
具体的には以下のメリット・デメリットがあるため、状況によっては司法書士への依頼が必要です。
相続登記を自分でやるメリット
相続登記を自分でやる場合、主なメリットは「費用の節約」です。
司法書士に依頼したときの費用は5万~15万円程度ですが、相続登記を自分でやると、出費は「必要書類の取得費+登録免許税」のみです。
登録免許税は分割納付できないため、現預金を取り崩したくないときは、相続登記を自分でやるとよいでしょう。
相続登記を自分でやるデメリット
相続登記を自分でやるときは、以下のデメリットを考慮してください。
- 必要書類の取得に時間がかかる
- 遺産分割協議書や登記申請書の作成ミスが発生しやすい
- 相続登記の期限に間に合わない
不動産や相続人の住所が離れていると、必要書類の取得に1年近くかかるケースもあります。
相続人が高齢だった場合は、死亡や認知症リスクも考えられるでしょう。
土地や建物が被相続人名義のままになると、不動産の活用・売却などに影響が出ます。
相続登記を自分でやるデメリットが大きい場合は、司法書士に依頼した方がよいでしょう。
まとめ
相続登記を自分でやった場合、費用の節約と引き換えに、時間や労力を消耗します。
仲の悪い相続人がいたり、不動産が遠方にあったりすると、相続登記の準備にストレスを感じてしまうでしょう。
2024年4月1日以降は、相続登記の期限にも注意が必要です。
相続登記を自分でやるかどうか迷ったときは、まず司法書士に相談してみましょう。
監修者プロフィール


代表池末 晋介(イケスエ シンスケ)
| 所有資格 |
司法書士 登録番号 第488号 簡裁訴訟代理業務認定番号 第401634号 |
|---|---|
| 所属団体 |
群馬司法書士会 全国クレジット・サラ金問題対策協議会会員 ぐんまクレジット・サラ金問題対策協議会幹事 |
| 経歴 |
群馬司法書士会 クレサラ・ヤミ金問題対策委員会委員長 群馬司法書士会 消費者委員会委員長 群馬司法書士会 理事 等を歴任 |
Contact
お問い合わせ



