法定相続人とは?範囲と順位や法定相続分をわかりやすく解説

2025年7月18日
目次
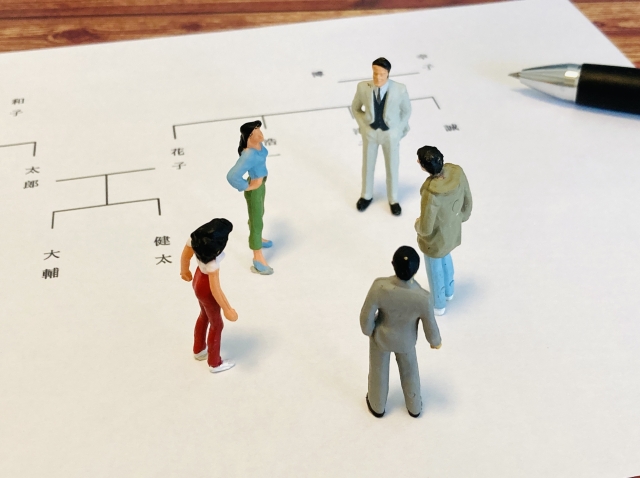
相続が発生したときは、法定相続人の確定が必要です。
法定相続人は一定範囲の親族に限られるため、誰が財産を相続できるのか、正しく理解しておきましょう。
本記事では、法定相続人の範囲と順位や、法定相続分などをわかりやすく解説します。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法に規定された相続権のある親族です。
遺言書がない相続では、被相続人(亡くなられた人)の配偶者や、一定範囲の親族が法定相続人となります。
相続が発生した場合、まず法定相続人の確定が必要になるため、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて集めてください。
なお、戸籍謄本をすべて集めても、相続を初めて経験する場合は、「法定相続人とはどこまでの範囲なの?」といった疑問が生じるでしょう。
法定相続人とは誰なのか、親族の範囲と相続順位は以下を参考にしてください。
法定相続人の範囲と相続順位
法定相続人の範囲は民法に定められており、以下のように相続順位も決まっています。
- 配偶者は必ず相続人となる
- 第1順位:直系卑属(子どもや孫など)
- 第2順位:直系尊属(父母や祖父母など)
- 第3順位:傍系(被相続人の兄弟姉妹や甥姪)
配偶者は必ず相続人となり、次は直系卑属(ちょっけいひぞく)が優先されます。
被相続人に配偶者と子どもがいる場合、直系尊属(ちょっけいそんぞく)となる父母や、傍系(ぼうけい)の兄弟姉妹は相続人になれません。
被相続人よりも先に子どもが死亡している場合でも、その子どもに子(被相続人の孫)がいると、代襲相続によって第1順位の法定相続人に繰り上がります。
代襲相続は被相続人の兄弟姉妹にも発生するため、甥や姪までが法定相続人の範囲です。
法定相続分(法定相続割合)とは
法定相続分とは、法定相続人が取得できる相続財産の割合です。
法定相続割合とも呼ばれており、以下のように相続人の状況で取得割合が異なります。
- 相続人が配偶者と子ども:配偶者1/2、子ども1/2
- 相続人が配偶者と被相続人の父母:配偶者2/3、父母1/3
- 相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
子どもの法定相続分は人数割りするため、2人いる場合はそれぞれ1/4(1/2×1/2)ずつ取得します。
なお、法定相続分は遺産分割の目安に過ぎないので、相続人全員の同意があれば、取得割合を自由に変更して構いません。
相続人や受遺者との違い
法定相続人は「相続権のある人」ですが、相続人は「実際に財産を相続する人」です。
相続権があっても、本人が相続を辞退すると、相続人にはなりません。
たとえば、父親が亡くなった際、「介護に専念していた母親が財産を多くもらうべきだ」などの理由で、子どもが相続を辞退するケースがあります。
子どもは法定相続人ですが、財産はもらっていないため、「相続人にならなかった」という状況です。
また、遺言書に則り財産をゆずることを「遺贈」といい、財産の承継者は「受遺者」と呼ばれます。
遺贈では受遺者を自由に指定できるため、第三者や代襲相続人ではない孫など、法定相続人以外が財産を取得するケースがあるでしょう。
法定相続人が遺産を相続できないケース
法定相続人は相続権を有していますが、必ずしも遺産を相続できるとは限りません。
被相続人の意向や、相続財産の状況によっては、以下のように相続できないケースもあります。
遺言書で受遺者に指定されなかった場合
遺言書による遺贈では、法定相続人を受遺者にしない場合があります。
たとえば、被相続人が全財産を第三者に遺贈したり、慈善団体などに寄付したりすると、法定相続人であっても財産を相続できません。
ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分があるため、法定相続分の1/2が保障されます(父母のみが相続人となる場合は1/3)。
遺留分は最低限の取得割合なので、遺言書で侵害された場合は、侵害している相手に返還請求できます。
相続放棄した場合
相続放棄すると、最初から相続人ではなかった扱いになるため、財産を取得できません。
相続財産には借金も含まれるので、返済義務を引き継ぎたくないときは、相続放棄を検討してもよいでしょう。
なお、相続放棄は家庭裁判所に申述する必要があり、手続きの期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内です。
相続放棄した人に子どもがいても、代襲相続人にはなれないので注意してください。
相続廃除された場合
相続廃除とは、相続権をはく奪される制度です。
たとえば、子どもから虐待されていた親が、「財産を渡したくない」と考えた場合、家庭裁判所に相続廃除を申し立てるケースがあります。
家庭裁判所が相続廃除を受理すると、子どもは相続権を失うため、相続人にはなれません。
廃除事由には侮辱や著しい非行などもあり、遺言書による相続廃除も可能です。
相続廃除は取消しできるので、相続人が改心した場合は、相続権が復活する可能性もあります。
相続欠格となった場合
相続欠格とは、相続人が以下の欠格事由に該当した場合、相続権をはく奪する制度です。
- 詐欺や強迫により、被相続人に遺言書の作成や撤回、取消しや変更などを行わせた
- 遺言書の偽造や変造、破棄や隠ぺいなどの行為があった
- 被相続人が殺害された事実を知りながら、告発・告訴をしなかった
- 意図的に被相続人を死亡させた
欠格事由に該当すると、被相続人の意思に関係なく、自動的に相続権がはく奪されます。
家庭裁判所の手続きも必要としないため、相続欠格になった場合、原則として相続権は復活しません。
法定相続人に関する注意点
家族構成が複雑になると、誰が法定相続人なのかわからなくなる場合があります。
法定相続人が遺産分割協議に参加できないケースもあるため、以下の注意点をよく理解しておきましょう。
養子縁組がある場合
養子がいる場合、養親が亡くなったときは第1順位の法定相続人になります。
法定相続分も実子と変わらないため、被相続人の戸籍謄本を取得したら、必ず養子縁組があるかどうか確認しましょう。
普通養子縁組であれば、養子は実親と養親どちらの財産も相続できます。
特別養子縁組の場合は実親との関係を断ち切っているため、養子は養親の財産しか相続できません。
法定相続人が未成年者の場合
法定相続人が未成年者だったときは、相続の際に代理人が必要です。
未成年者は法律行為が制限されるため、相続手続きや遺産分割協議などに対応できません。
一般的な法律行為は親権者(親)が法定代理人となりますが、相続では利益相反関係が生じます。
親と未成年の子が相続人になる場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立ててください。
胎児がいる場合
民法では胎児の相続権を認めており、無事に生まれた場合は相続人になります。
胎児はすでに生まれた人として扱われるため、遺言書による遺贈や代襲相続、相続放棄も可能です。
相続放棄は母親が胎児の法定代理人になれますが、遺産分割協議に参加するときは、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てましょう。
法定相続人が行方不明の場合
行方不明の法定相続人がいる場合は、市町村役場で戸籍の附票を取得してください。
戸籍の附票には住所の変更履歴が記載されるため、住民登録している現住所がわかります。
現住所を確認したら、訪問や手紙により、相続発生や遺産分割協議への参加を連絡しておきましょう。
行方不明者が未婚だった場合は、親の戸籍謄本で住所を確認できます。
なお、行方不明者の直系血族(子どもや父母)は戸籍の附票を取得できますが、傍系(兄弟姉妹)からの請求には基本的に応じてもらえません。
戸籍や住所情報の取得が難しいときは、司法書士などの専門家に職権請求してもらいましょう。
法定相続人がいない場合
法定相続人がいないケースでは、利害関係者からの申し立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。
相続財産清算人は公告によって相続人や債権者を探しますが、誰もいなければ相続財産を国庫に帰属させます。
被相続人と同一生計で暮らすなど、家族同然と認められる特別縁故者がいる場合は、家庭裁判所が財産分与の申し立てを認めるケースもあります。
まとめ
法定相続人は戸籍謄本を辿って調べますが、登場人物が多くなると、相続権の有無を間違える場合があります。
各自の法定相続分もわかりにくくなるため、遺言書を作成した際、遺留分を侵害する恐れもあるでしょう。
法定相続人の確定や、法定相続分の判断などに困ったときは、司法書士などの専門家に相談してください。
監修者プロフィール


代表池末 晋介(イケスエ シンスケ)
| 所有資格 |
司法書士 登録番号 第488号 簡裁訴訟代理業務認定番号 第401634号 |
|---|---|
| 所属団体 |
群馬司法書士会 全国クレジット・サラ金問題対策協議会会員 ぐんまクレジット・サラ金問題対策協議会幹事 |
| 経歴 |
群馬司法書士会 クレサラ・ヤミ金問題対策委員会委員長 群馬司法書士会 消費者委員会委員長 群馬司法書士会 理事 等を歴任 |
Contact
お問い合わせ



