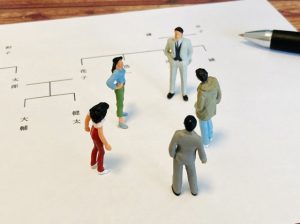おひとりさまの遺産は誰のもの?相続人がいない人の生前対策を解説

2025年7月18日
目次

おひとりさまの遺産は、最終的には国庫に帰属します。
兄弟姉妹が相続人になるケースもあるので、遺産の承継者を早めに確かめておきましょう。
本記事では、おひとりさまの遺産を相続する人や、生前対策をわかりやすく解説します。
おひとりさまの遺産を相続できる人
おひとりさまの遺産は、基本的に法定相続人が相続します。
別居している子どもや父母がいる場合等、法定相続人がいる場合はその方が相続人となります。
法定相続人がいなくても、遺言書を活用すると、親しい友人などに遺産を渡せます。
おひとりさまの遺産を相続できる人や、遺言書で遺産を渡せる人は以下を参考にしてください。
法定相続人
おひとりさまに別居中の法定相続人がいる場合は、遺産の承継者となります。
法定相続人とは、民法に定められた相続権のある親族です。
配偶者は常に相続人となりますが、離婚や死別で配偶者がいないときは、以下の順位で法定相続人が決まります。
- 第1順位の法定相続人:子ども(いない場合は孫やひ孫など)
- 第2順位の法定相続人:父母(いない場合は祖父母など)
- 第3順位の法定相続人:兄弟姉妹(いない場合は甥姪)
相続の際には直系卑属(ちょっけいひぞく)が優先されるため、子どもが生きていると、父母や兄弟姉妹は相続人になれません。
おひとりさまに子どもや孫、父母や祖父母などもいなければ、兄弟姉妹に相続権が発生します。
兄弟姉妹が死亡しているときは、甥・姪が法定相続人です。
遺言書による受遺者
おひとりさまの遺産を相続する人がいないときは、遺言書の作成を検討してみましょう。
遺言書では受遺者(財産の承継者)を自由に指定できるため、お世話になった友人や知人などに遺産を渡せます。
ただし、法定相続人がいる場合は、遺留分の侵害に注意してください。
遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に保障されており、必ず取得できる遺産の割合です。
特定の受遺者だけに遺産を集中させると、遺留分を侵害する恐れがあります。
遺留分の侵害は相続トラブルの原因になるため、遺言書を作成するときは、遺産の配分に注意しましょう。
おひとりさまに相続人がいないときの遺産の扱い
おひとりさまに相続人や受遺者がいない場合は、家庭裁判所が利害関係者からの申し立てにより、相続財産清算人を選任します。
家庭裁判所と相続財産清算人の公告により、相続人が見つかったときは遺産を相続してもらえる可能性があります。
相続人が見つからなかった場合は、おひとりさまの遺産が以下のよう処分されます。
債権者への弁済
おひとりさまに債権者がいる場合は、遺産を弁済に充てます。
現金・預金の不足によって弁済できないときは、相続財産清算人が不動産などを売却し、資金を準備する場合もあります。
特別縁故者への財産分与
特別縁故者とは、被相続人(亡くなられた人)と同一生計だった場合など、特別な関係にあった人を指します。
おひとりさまに特別縁故者がいる場合は、家庭裁判所に財産分与を申し立て、遺産の一部または全部を取得できるケースがあります。
ただし、同一生計や療養看護などの証拠がなければ、家庭裁判所が特別縁故者を認めてくれないでしょう。
特別縁故者を主張するときは、医療費や介護費用の領収書や、同一住所の住民票などが必要です。
国の財産になる
おひとりさまに相続人や特別縁故者などがいなければ、遺産が国庫に帰属します。
国の財産になると、遺産の放置状態を回避できますが、何の財源になるのかはわかりません。
国庫への帰属を望まないときは、遺言書による寄付などを考えてもよいでしょう。
おひとりさまの遺産に関するトラブル
おひとりさまが亡くなると、遺産に関するトラブルが発生しやすくなります。
不動産がある場合は、取得を希望する相続人がいない、処分もできないといった問題が発生する場合もあります。
具体的には、以下のようなトラブルが想定されます。
相続財産の調査が難しくなる
おひとりさまの相続が発生した場合、別居している親族や第三者では、相続財産の調査が困難です。
預金通帳や印鑑などの保管場所がわからなければ、家の中を徹底的に調べる必要があるでしょう。
ネット銀行の預金や、電子化された証券などは「デジタル遺品」と呼ばれており、IDやパスワードを知らない人には調査が困難になります。
おひとりさまのみで財産を管理していると、生命保険の契約なども見逃されてしまうリスクがあります。
遺産分割協議を開始できない
おひとりさまの財産調査が難航すると、遺産分割協議を開始できない恐れがあります。
遺言書がない相続では遺産分割協議を行いますが、財産の全容がわからない状況では、相続人間で話し合いを開始できません。
甥や姪が相続人になるケースでは、「誰が法定相続人を調べるのか?」「どこで遺産分割協議をする?」などの問題も生じるでしょう。
遺産分割協議を開始できない場合、期限付きの相続手続きに間に合わない可能性があります。
相続手続きが放置される
おひとりさまが亡くなった場合、相続手続きが放置されるケースもあります。
親族が遠方に住んでいると、以下の相続手続きに対応が困難になります。
- 相続登記:不動産の所在地を管轄する法務局が窓口
- 相続税申告:被相続人の最後の住所地を管轄する税務署が窓口
預貯金を相続する際も、被相続人が地方銀行で口座開設していると、相続人が住む地域に支店がないかもしれません。
郵送扱いに対応した相続手続きもありますが、提出書類の書き方などを詳しく聞きたいときは、窓口に出向いた方がよいでしょう。
おひとりさまの生前対策
おひとりさまの遺産はトラブルの原因になりやすいため、生前対策が必要です。
早めに準備すると、誰にどの財産を受け取ってほしいのか、自分の考え方も明確になります。
では、今からでもできる生前対策をみていきましょう。
財産目録を作成する
財産目録があると、預金口座や不動産の情報がすぐにわかります。
自分の財産をノートなどに書き出し、関連資料も添付しておけば、相続人や第三者に役立ててもらえます。
なお、相続財産には負債も含まれます。
返済しきれない借金や未払金がある場合も、財産目録に記載しておきましょう。
推定相続人を確かめる
推定相続人とは、相続人になることが想定される親族です。
戸籍を辿って推定相続人を確認し、家系図を作成すると、誰に相続権があるのか判断できます。
兄弟姉妹の戸籍謄本は取得できませんが、未婚の場合は親の戸籍に入っています。
家系図に住所や電話番号も記載しておけば、遺産分割協議の招集もスムーズになるでしょう。
遺言書を作成する
遺言書には強制力があるため、自分が望んだとおりの遺産相続を実現できます。
遺産の承継先が決まったら、遺言書を作成してみましょう。
ただし、遺言書の書き方や修正方法を間違えると、無効になる可能性があるので要注意です。
確実な遺言書を作成したいときは、公証役場で公正証書遺言にするとよいでしょう。
司法書士などに遺言執行者を依頼しておけば、遺言書の内容を間違いなく実現することができます。
任意後見人を決めておく
元気なうちに任意後見人を決めると、認知症リスクに備えられます。
認知症になった後は法定後見人しか設定できませんが、任意後見人は自分で選べます。
信頼できる親族や知人がいる場合は、早めに任意後見契約を結んでおくとよいでしょう。
仮に認知症になったとしても、法律行為や財産管理は任意後見人が代行してくれます。
まとめ
おひとりさまが亡くなると、日頃は付き合いのない親族や、第三者が遺産を取得します。
しかし、財産の種類や法定相続人がわからなければ、相続手続きが困難になります。
甥や姪が相続する場合は、戸籍謄本の取得だけでも大きな負担になります。
親族に負担をかけず、スムーズな遺産相続にしたいときは、司法書士などの専門家に生前対策を相談してください。
監修者プロフィール


代表池末 晋介(イケスエ シンスケ)
| 所有資格 |
司法書士 登録番号 第488号 簡裁訴訟代理業務認定番号 第401634号 |
|---|---|
| 所属団体 |
群馬司法書士会 全国クレジット・サラ金問題対策協議会会員 ぐんまクレジット・サラ金問題対策協議会幹事 |
| 経歴 |
群馬司法書士会 クレサラ・ヤミ金問題対策委員会委員長 群馬司法書士会 消費者委員会委員長 群馬司法書士会 理事 等を歴任 |
Contact
お問い合わせ