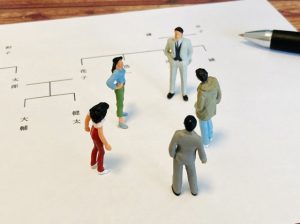遺産分割協議とは?協議のやり方や困ったときに相談できる専門家を解説

2025年7月18日
目次

遺産分割協議とは、遺言書がないときに必要な相続人全員の話し合いです。
協議に参加する人や、話し合う内容を理解すると、相続手続きがスムーズになるでしょう。
本記事では、遺産分割協議の進め方や、困ったときに相談できる専門家を詳しく解説します。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、遺産の分け方を決める話し合いです。
遺言書がない場合は、相続人全員の協議により、「誰がどの財産を相続するのか」または「誰がどの割合で相続するのか」を決定します。
なお、遺言書が作成されていても、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議で財産の分け方を決められるけーすもあります。
各相続人の住所が離れている場合は、電話やメール、オンラインミーティングで遺産分割協議を進めてもよいでしょう。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必要
遺産分割協議を行う際は、相続人全員の参加が必要です。
相続人が1人でも欠けていると、遺産分割協議は無効となります。
一部の相続人を除外して遺産分割協議を進めた場合、トラブルの原因にもなるので注意してください。
仲が悪い相続人がいる場合でも、必ず遺産分割協議に参加してもらいましょう。
相続分を放棄する人も遺産分割協議に参加する
相続分の放棄とは、法定相続分を受け取らず、他の相続人に配分する行為です。
簡単にいうと、何も相続しない状況ですが、相続分を放棄する人も遺産分割協議への参加が必要です。
相続分を放棄しても、相続人の地位には影響がないため、被相続人(亡くなった人)に借金があった場合は、返済義務を引き継がなくてはなりません。
遺産分割協議書を作成する際も、相続分の放棄を記載して、署名捺印する必要があります。
なお、相続分の放棄は相続人同士の取り決めですが、「相続放棄」は家庭裁判所を介した手続きです。
相続放棄が認められると、預貯金や不動産などは相続できませんが、借金の返済義務も免除されます。
遺産の分割方法
遺産分割協議では、以下の方法で遺産を分割します。
- 現物分割:相続財産を現物の状態で分割(相続)する方法
- 共有分割:法定相続分に応じた持分割合で不動産などを共有する方法
- 換価分割:不動産などの売却代金を分割する方法
- 代償分割:代償金の支払いにより公平に遺産分割する方法
現物分割の場合、預金口座などをそのままの状態で相続します。
共有分割は複数の相続人で不動産を分割する方法ですが、売却などの契約行為には全員の合意が必要になるため、十分な検討が必要です。
主な相続財産が不動産しかなく、複数の相続人がいる場合は、換価分割や分割方法を検討してみましょう。
遺産分割協議のやり方
遺産分割協議をやるときは、入念な下準備が必要です。
法定相続人や相続財産の調査が完了していると、協議が進みやすくなるでしょう。
具体的な遺産分割協議のやり方は、以下を参考にしてください。
法定相続人の確定
遺産分割協議をやる場合は、まず法定相続人を確定させましょう。
法定相続人は範囲と順位が決まっており、以下のように配偶者と上位の親族のみが該当します。
- 配偶者は常に相続人となる
- 第1順位:子ども
- 第2順位:父母
- 第3順位:兄弟姉妹
養子や前妻との間に生まれた子、認知された非嫡出子も第1順位の法定相続人になるため、遺産分割協議への参加が必要です。
相続財産の調査
相続財産を調査するときは、以下の財産をすべて洗い出します。
- 現金や預貯金
- 株式
- 不動産
- 著作権などの知的財産権
- 自動車
- 貴金属や美術品
- 借金
預金通帳やキャッシュカードがあれば、口座番号と取引銀行がわかります。
株式は電子化されているため、差出人が証券会社の郵便物を調べてみましょう。
不動産をすべて把握したいときは、市町村役場で名寄帳を取得してください。
次に法務局で登記事項証明書を取得すると、不動産の詳細情報を確認できます。
借金はマイナスの相続財産となるため、借用書や督促状も探しておきましょう。
相続人全員による協議
法定相続人と相続財産の調査が完了したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
協議を進める際には、戸籍謄本や登記事項証明書など、関係資料をすべて開示してください。
相続する割合が決まらないときは、以下の法定相続分を目安にします。
- 相続人が配偶者と子ども:配偶者1/2、子ども1/2
- 相続人が配偶者と被相続人の父母:配偶者2/3、父母1/3
- 相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
相続財産は公平に分けられないケースが多いため、被相続人を介護していた人には多めに配分するなど、ある程度の譲歩が必要なばあいもあります。
遺産分割協議書の作成
相続人全員が遺産分割協議に合意したら、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
遺産分割協議書は適宜の様式で構いませんが、以下の項目は必ず記載します。
- 遺産分割協議書(表題)
- 被相続人の氏名と死亡日
- 被相続人の本籍地と死亡時の住所
- 誰が・どの財産を相続するか
- 相続財産の詳細情報
- 新たな財産が見つかったときの扱い
- 遺産分割協議の成立日
- 相続人全員の署名捺印(実印を使用)
遺産分割協議書の書き方がわからないときは、司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。
遺産分割協議書が完成したら、実印の証明として、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議を行う場合、相続人の状況によっては特別代理人が必要です。
成年後見人を選任するケースもあるため、以下の注意点をよく理解しておきましょう。
遺産分割協議の期限
遺産分割協議に期限はありませんが、相続手続きの期限に注意が必要です。
以下の相続手続きには期限があるため、間に合うように協議を進めてください。
- 相続税申告:相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
- 相続登記:不動産の相続人が確定してから3年以内
相続税申告の期限を過ぎると、本来納めるべき税金に延滞税などが加算されます。
期限後の相続登記は10万円以下の過料になる恐れがあるため、早めに手続きを済ませておきましょう。
借金の負担割合は法定相続分に応じる
相続財産に借金がある場合、返済負担は法定相続分に応じます。
遺産分割協議で借金の負担割合を決めたとしても、債権者には通用しません。
一部の相続人だけで借金を相続したい場合は、債権者の承認が必要です。
認知症の相続人を交えた遺産分割協議は無効
認知症の相続人も遺産分割協議に参加できますが、協議がまとまったとしても無効です。
すでに認知症となった相続人がいるときは、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立ててください。
成年後見人が選任されると、本人の代理人として遺産分割協議に参加してもらえます。
未成年者の相続人には特別代理人が必要
未成年者とその親が相続人になる場合は、未成年者に対して特別代理人の選任が必要です。
親は未成年の子の法定代理人ですが、相続では利益相反の関係になるため、遺産分割協議の際に親は子の代理人になれません。
特別代理人には資格要件がないので、法定相続人ではない親族(伯父・伯母など)を選任できます。
親族から特別代理人を選任できないときは、司法書士などの専門家に依頼してみましょう。
遺産分割協議で困ったときに相談できる専門家
遺産分割協議で困ったときは、以下の専門家に相談してください。
- 弁護士:相続トラブルが発生した場合
- 税理士:相続税が発生する場合
- 司法書士:相続登記や相続手続き全般を任せたい場合
弁護士は紛争解決を専門としており、遺産分割調停を申し立てる際も、依頼者の代理人にもなってもらえます。
相続税申告は税務調査の対象になりやすいため、不安がある方は、税理士に代行してもらいましょう。
不動産の相続登記を任せたいときは、司法書士に相談してください。
司法書士は業務範囲が広いので、遺産分割協議書の作成や、財産調査も依頼できます。
まとめ
遺産分割協議のやり方には一定のルールがあるため、相続人や相続財産の状況をよく確認してください。
未成年者や認知症の相続人が参加していると、遺産分割協議は成立しません。
相続手続きの期限が迫っている場合は、1日でも早く協議をまとめる必要があります。
遺産分割協議に困ったときは、司法書士などの専門家に相談してみましょう。
監修者プロフィール


代表池末 晋介(イケスエ シンスケ)
| 所有資格 |
司法書士 登録番号 第488号 簡裁訴訟代理業務認定番号 第401634号 |
|---|---|
| 所属団体 |
群馬司法書士会 全国クレジット・サラ金問題対策協議会会員 ぐんまクレジット・サラ金問題対策協議会幹事 |
| 経歴 |
群馬司法書士会 クレサラ・ヤミ金問題対策委員会委員長 群馬司法書士会 消費者委員会委員長 群馬司法書士会 理事 等を歴任 |
Contact
お問い合わせ