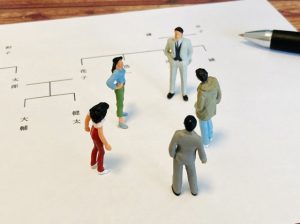配偶者居住権とは?メリット・デメリットを解説

2025年7月18日
目次
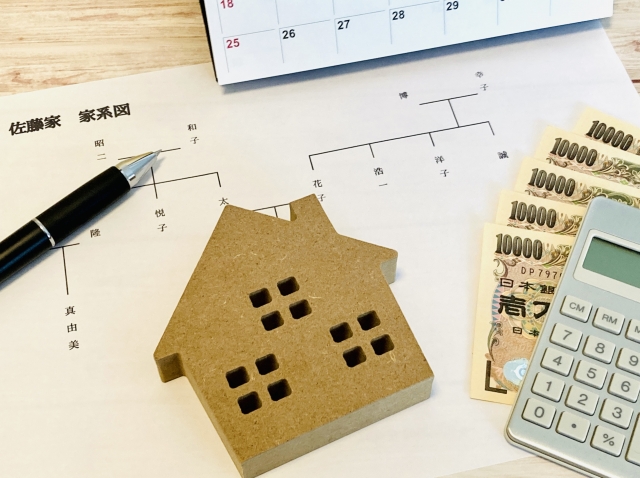
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった(被相続人)場合、残された配偶者(相続人)が、被相続人の所有する建物に、生涯または一定期間、無償でそのまま住み続けられる権利をいいます。
不動産の所有権には、法令の範囲内において、不動産を自由に使用、収益、処分ができる権利があります。
相続の際に配偶者居住権を活用すると、「住む権利」を「配偶者居住権」、「その他の権利」を「所有権」として分離し、別の人がそれぞれ権利を持ちます。
つまり、配偶者居住権者は、その住居に無償で住み続ける権利がありますが、不動産の所有者ではないため、第三者に売却することはできません。
一方、所有権は「配偶者居住権」以外のすべての権利をいい、その不動産の登記上の所有者です。
本来であれば、不動産の所有者は、その不動産を自由に売却することができます。しかし、配偶者居住権が設定されている場合、居住者の同意がなければ売却することはできません。また、固定資産税の納税義務もあります。
配偶者居住権が法制化された背景
配偶者居住権は、2020年4月の改正民法の際に新設されました。
高齢化が進み平均寿命も延びていることから、残された配偶者はさらに長い期間生活していかなければなりません。そのため、配偶者が住み慣れた住居で長く住み続けることができ、かつ生活資金のための預貯金も確保することが必要となっています。
従来の制度では主に3つの方法がありましたが、それぞれ問題点がありました。
| 方法 | 問題点 |
| ①建物の所有権を相続する。 | 不動産評価額が高いと、それのみで相続分になってしまい、預貯金などが取得できず生活が困難になる可能性がある。 |
| ②建物の所有権を相続した者から家賃を払って借りる(賃借)。 | 毎月賃料を払うと生活が困難になる可能性がある。 |
| ③建物の所有権を相続した者から無償で借りる(使用貸借)。 | 建物所有権を相続した者が売却した場合、第三者に対抗できないため、退去しなければならない。 |
そこで、配偶者の待遇を改善するための「配偶者居住権」が新設されました。
不動産を「居住権」と「所有権」に分けて考えることで、配偶者は所有権がなくても、居住権の取得によって住み慣れた住居に住むことができます。さらに、生活資金を相続しやすくすることで、生活リスクが軽減できるようになりました。
配偶者居住権のメリット
配偶者居住権のメリットは主に3つあり、以下のとおりです。
1. 現在の家に終身無償で住み続ける事ができる
配偶者居住権を取得すれば、配偶者が亡くなるまでの間、賃料を払うことなく住み続けることができます。
例えば、配偶者と子の関係が悪く、子が自宅の所有権を相続した場合、「出ていってほしい」と言われたり、子が自宅を売却してしまったりして、自宅から追い出される可能性があります。
しかし、配偶者居住権を設定しておくことで、配偶者は追い出されることなく住み続けることができます。さらには、法務局で配偶者居住権を登記しておくことで、万が一、子が自宅を売却しても、登記によって「住む権利」が主張でき、第三者に対抗できます。
2. 預貯金等の財産が取得できる
法改正前の場合、配偶者が不動産を相続することが一般的であり、不動産評価額によっては預貯金などの生活資金が確保できませんでした。
例えば、不動産4,000万円+預貯金4,000万円=合計8,000万円で、相続人が配偶者、子1人だったとします。
4,000万円ずつ分けるためには、配偶者が不動産、子が現金で公平となります。しかし、これでは配偶者の今後の生活資金がありません。
そこで配偶者居住権を活用します。仮に配偶者居住権の評価額が2,000万円で、所有権が2,000万円だったとすると、配偶者は2,000万円の配偶者居住権と預貯金2,000万円の合計4,000万円を相続することになり、住居も生活資金も確保できます。
3. 代償金を減らせる
配偶者が不動産を相続し、不動産評価額が配偶者の法定相続分を上回った場合、配偶者は他の相続人に代償金を支払わなければなりません。
例えば、不動産4,000万円+預貯金1,000万円=合計5,000万円で、相続人が配偶者、子1人だったとします。
法定相続分で相続すると2,500万円ずつとなりますが、配偶者が不動産を相続すると、子に
1,500万円の代償金を支払わなければならなくなり、不動産を売却せざるを得なくなる可能性があります。
そこで配偶者居住権を活用します。仮に配偶者居住権の評価額が2,000万円だった場合、預貯金500万円が相続でき、子も所有権2,000万円と預貯金500万円を相続できます。
配偶者は代償金を支払うことなく、住居も生活資金も確保できます。
配偶者居住権のデメリット
配偶者居住権のデメリットは主に4つあり、以下のとおりです。
1. 不動産の譲渡・売却ができない
配偶者居住権は「住む権利」であるため、配偶者が不動産を譲渡・売却することはできません。また、所有者の許可なくして賃貸することもできません。
そのため、老人ホームに入居するための資金が欲しいからといって、配偶者が自宅を譲渡・売却することはできないことになります。
所有者側からしても、配偶者居住権が設定されている場合、不動産の譲渡・売却は難しくなります。存続期間が配偶者の終身となっている場合、売却したくてもそもそも買主を見つけることが難しくなります。
2. 所有者にも税負担がある
固定資産税の納税義務者は所有者となっています。
ただし、法改正後では、居住建物の「通常の必要費」は配偶者が負担すると定められています(1034条)。「通常の必要費」には建物の修繕の他に、固定資産税も含まれると考えられています。
そのため、建物の所有者が建物の固定資産税を納付した場合には、配偶者に対して納付分を請求することができますが、土地の固定資産税は所有者が住んでいなくても所有者が支払うことになります。
3. 配偶者が若いと配偶者居住権の恩恵が少なくなる
配偶者居住権の評価額の計算式に必要な「存続年数」とは配偶者居住権の存続年数をいい、配偶者が亡くなるまでとした場合、平均余命が存続年数です。そのため、配偶者が若いと平均余命も長くなります。
また、建物の築年数が古い場合、「建物の評価額 = 配偶者居住権の評価額」となります。
つまり、配偶者の年齢や建物の築年数によっては居住権の価値が高くなり、相続できる預貯金が少なくなる可能性があります。生活費を確保できるはずの配偶者居住権の恩恵が減少してしまうかもしれません。
4. 配偶者居住権は法律上の配偶者のみ
配偶者居住権は法律上の配偶者のみの権利であり、内縁(事実婚)の配偶者には認められていません。
内縁の配偶者に住居を残すためには、以下の方法があります。
① 遺言書を作成して、内縁の配偶者に遺贈する旨を記載する。
② 生前贈与をする。
③ 建物所有者に法定相続人がひとりもいない場合は、特別縁故者として遺産を取得する。
内縁の配偶者には認められていないとはいえ、一定程度保護される判例もあるようです。相続人から不当に明渡しを請求されたら、「権利の濫用」を主張することが可能な場合があります。
まとめ
配偶者居住権は、配偶者が住み慣れた住居で無償で住み続けることができ、老後資金のための預貯金も確保できる制度です。
一方で、不動産の譲渡・売却がしにくくなったり、配偶者の年齢や築年数によっては相続できる預貯金が少なくなったりとデメリットもあります。
配偶者とその他の相続人との関係性も含め、慎重に考慮することが大切です。
監修者プロフィール


代表池末 晋介(イケスエ シンスケ)
| 所有資格 |
司法書士 登録番号 第488号 簡裁訴訟代理業務認定番号 第401634号 |
|---|---|
| 所属団体 |
群馬司法書士会 全国クレジット・サラ金問題対策協議会会員 ぐんまクレジット・サラ金問題対策協議会幹事 |
| 経歴 |
群馬司法書士会 クレサラ・ヤミ金問題対策委員会委員長 群馬司法書士会 消費者委員会委員長 群馬司法書士会 理事 等を歴任 |
Contact
お問い合わせ